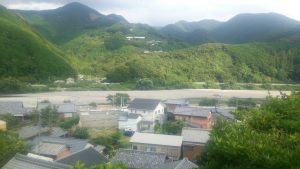地球外知的生命体が地球にくるとしたらその背景と可能性を考えてみた。 なお、太陽系内にはいなそうなので太陽系外と同一と考える。
1.相対性理論の要請から、ともかく遠いし時間がかかる。
2.地球の回転速度の20倍でも光速の0.1%
従って、20光年以内にあったとしても2000年かかる
片道1万年かかると思わなければならない
加速だけではなく減速にも燃料がいるし時間がかかる。
3.恒星間飛行が可能な知的生命体になるには、水・大陸・酸素は
必要そう。また、エネルギー源は安定性から光になりそう。
4.1の事から、バクテリアや岩石内バクテリアや真菌的なものを載せた
ロケットを載せるぐらいか、その恒星系に重大なモンダイが予見される
場合しか知的生命体が飛び出すことは考えられない。
5.従って、どこかへの移住できればという目的しかない。1の事から
岩石系惑星か衛星、出来ればハビタブルゾーンが見つかればそこに
移住を決める。いくつかも試せれない。 しかも何十、何百世代
かかって着いた。 その間のエネルギーをどう持たせるかかと
いうのもある。
6.食料は、人工のものか家畜や野菜を積んでいると思われる。
7.どこの惑星・衛星が良いかになる。太陽系では、地球か火星か
月ぐらいが候補となると思われる。
第一段階は、エンケラドスで水(氷)の確保
(核融合、及びロケットエンジンの燃料用として)
8.その後、静止衛星の2~3倍の距離のところで周回軌道にのる
9.武器・人間を攻撃、その際、他の生物ごとでも可。
テラフォーミング的な事を行うので水さえ確保できれば、
例えば、小惑星をぶつけるのもあり
10.減速・加速も大変なので、良い惑星があるかどうか観測可能か?
あるいは通り過ぎて戻ってくるか
11.一番ありそうなのは、電波でやり取りするくらい
12.量子テレポーションは難しそうなので、3Dプリンターを利用して
バクテリアかマイクロロボットを送りこむ。
あるいはコンピュータをハッキングして侵略(文明・文化のみを
伝播)
13.進数?で、数、数字、何進法かを教えあう。次に2値画像を送る。
文字を送る。自然単語を送る
いくつかの動詞を送る。
ここからが大変かも
14.コンピュータ上に意識を載せたもの、あるいは、生命の合成に成功して
コンピュータにその生成方法を載せて恒星間飛行をする。
カタパルトで発進する。加速度を大きくできる。それでもせいぜい
0.0001Cぐらいの速度なので、20万年ぐらいかかる。